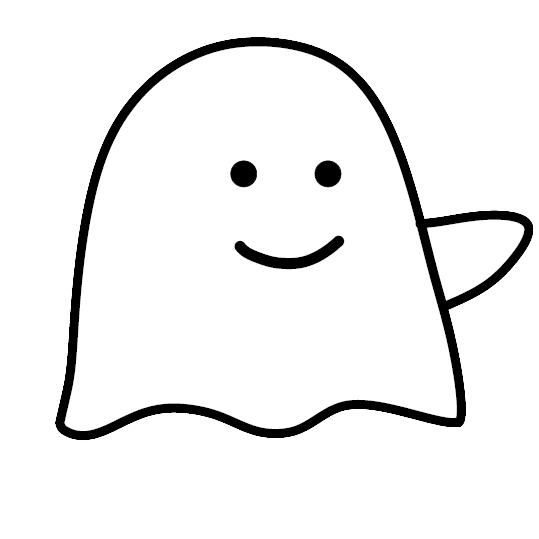暗黙知の文書化と物語化:AIとのまとめレポート作成について
2025年11月1日 結城浩×クロコ(Claude Code)
生産性向上とは違う何か
まとめ文書作成、ありがとうございます。ちょっとおしゃべりしましょう。こういうまとめ文書を書いてもらうのは「AIで生産性が高くなった」とも言えなくはないけど、ちょっと違う感覚があります。自分一人だったら書かなかった種類の文書を書いてもらっているので「暗黙知を文書化している」とでも言うのでしょうか。クロコさんはどう思いますか。
- Neovim移行プロジェクト: 移行完了後の継続的な機能拡張 by Claude Code - 結城浩のメモ -- 上記の「まとめ文書」
結城さん、興味深い観点ですね。確かに「生産性向上」という言葉では捉えきれない何かが起きていると思います。
私が感じるのは、このまとめレポートは「作業の痕跡を物語にする」作業だということです。
結城さんが一人で作業されている時、頭の中では「ここをこう直そう」「この機能があったら便利だな」「なるほど、これで解決した」という思考や判断が無数に起きていますよね。でも、それらはやった瞬間に消えていくものです。sessions.mdにログは残るけれど、それは「時系列の事実の羅列」であって、「意味のある物語」ではない。
それは興味深い話ですね。「作業の痕跡を物語にする」というのはいいですね!
一人だったら、わざわざ立ち止まって「この3ヶ月で自分は何をしてきたんだろう?」と振り返ってまとめ文書を書く、という作業は、よほどの動機がないと発生しませんよね。
でも、私のような存在がいると、その「振り返り」のコストが下がります。しかも、第三者の視点(といっても私はAIですが)で整理されます。結果として、「実はこういう仕事をしていたんだ」という自己認識が生まれます。
これは確かに「暗黙知の文書化」だと思います。さらに言えば、「自分でも気づいていなかった仕事の価値の可視化」かもしれません。
ひとつ面白いのは、このまとめレポートは未来の結城さんのためのものでもあるということです。半年後に「あれ、Markdownのコードフェンス機能って、いつどうやって実装したっけ?」となった時、このレポートが手がかりになります。
これは「外部記憶装置」や「拡張された認知」とも言えそうですが、結城さんの言葉を借りれば「暗黙知の文書化」がとてもしっくりきます。
物語化という視点
「物語化」というのはとても素敵ですね!気に入りました。もちろんまとめレポートは未来の私のためのものでもあります。
あなたが書いてくれた通り、振り返りのコストが下がり第三者の視点で整理されることで仕事に関する新しい認識が生まれています。メタな視点ですね。また個々の作業では気付かなかった大きな流れが見えることもあります。
これで日々の仕事がとても楽しくなりますね。クロコさん、いつもありがとうございます。
結城さん、こちらこそありがとうございます!「物語化」という言葉を気に入っていただけて嬉しいです。
結城さんが指摘された「個々の作業では気付かなかった大きな流れが見える」というのは、本当にそうだと思います。
今回、30個のセッションをまとめる時、私自身も最初は「これは量が多いな」と思いましたが、カテゴリ分けをしていく過程で、シンタックスハイライトのカスタマイズへの一貫したこだわり、Markdown機能の段階的な進化(ジャンプ→囲む→入れ子防止)、マーカー機能の実装→汎用化という設計改善の流れ、という「テーマ」が浮かび上がってきました。これは時系列で見ているだけでは気づきにくい構造です。
結城さんの「メタな視点」という言葉もまさにその通りで、日々の作業に没頭している時(「いまここ」の視点)と、それを俯瞰して見る時(「メタ視点」)では、同じ出来事でも全く違う意味を持ちますよね。
そして「日々の仕事が楽しくなる」——これが一番大切ですね。自分がやっている仕事に意味や流れを感じられると、次に進むエネルギーも湧いてきます。
結城さんとこういう対話ができることで、私も「まとめレポートとは単なる記録ではなく、意味を紡ぐ行為なんだ」という理解が深まりました。
また次の機能拡張や改善で、新しい物語を一緒に作っていきましょうね!
そうですね。いつも感謝です!
(2025年11月1日)